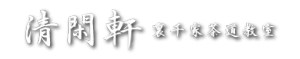「茶道」は禅仏教から大きな影響を受けております。
一方、墨蹟、花、陶磁器、漆器、金属・竹細工美術品、建築、造園、料理、織物などの、
日本文化における様々な分野とも関わっているため、
日本文化の多くの面に影響を及ぼして参りました。
このように「茶道」は、日本の土壌に培われて、
日本の美学と文化の本質を表しておりますゆえに、
さまざまな伝統文化を集成した総合芸術だと言われております。
また「茶道」は、「茶禅一味」という言葉に表されますように、
禅の思想に大きな影響を受け精神的な面をもっとも大切にしています。
そして、茶道の精神は、四規『和・敬・清・寂』
この四つの文字により全て表わされていると言われております。
和(わ) – お互いに心を開いて仲良くする、和し合う心
敬(けい) – 尊敬の敬で、お互いが敬い合う心
清(せい) – 清らかの意、見た目だけではない、その心
寂(じゃく) – どの様な時にも動じない、静寂な心
現代は、残念ながら、日々を心せわしく過ごし、
自然に接することも少なく、人が人を大切に出来なくなり、他人を傷つけ、
自分のことしか考えられない人が多くなりました。
こうした世の中だからこそ、私たちは茶道を通じて、
心から友と語らい、自らを見つめなおすひとときを
持つことが大切なのではないでしょうか。
福原宗貴 福原宗邦



利休七則(りきゆうしちそく)
茶は服のよきように点て
炭は湯の沸くように置き
花は野にあるように
夏は涼しく冬は暖かに
刻限は早めに
降らずとも雨の用意
相客に心せよ
この教えは、千利休の弟子の一人が「茶の湯で心得ておくべき最も大切なことはなんでしょうか」と利休に尋ねたことに答えたものです。
ところが、その答えが当たり前すぎたので「そんなことは誰もが知っています」と不服そうに言いますと、利休は「私がいったことにかなう茶ができたなら、
あなたの弟子になりましょう」と諭しました。
このように、誰にでもわかっていることでも、いざ実行しようとすると
大変難しいことでありますので、普段から平易なことであっても、
実行するよう心がけることが大切だということを教えています。